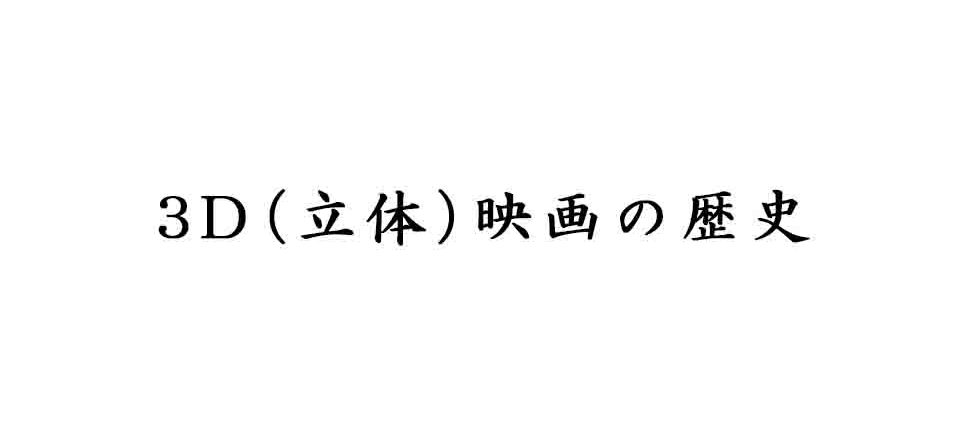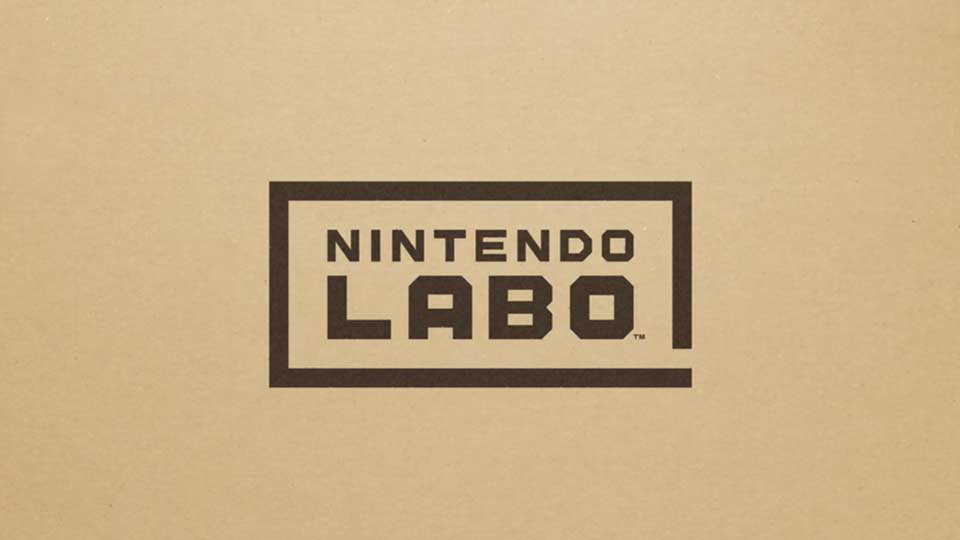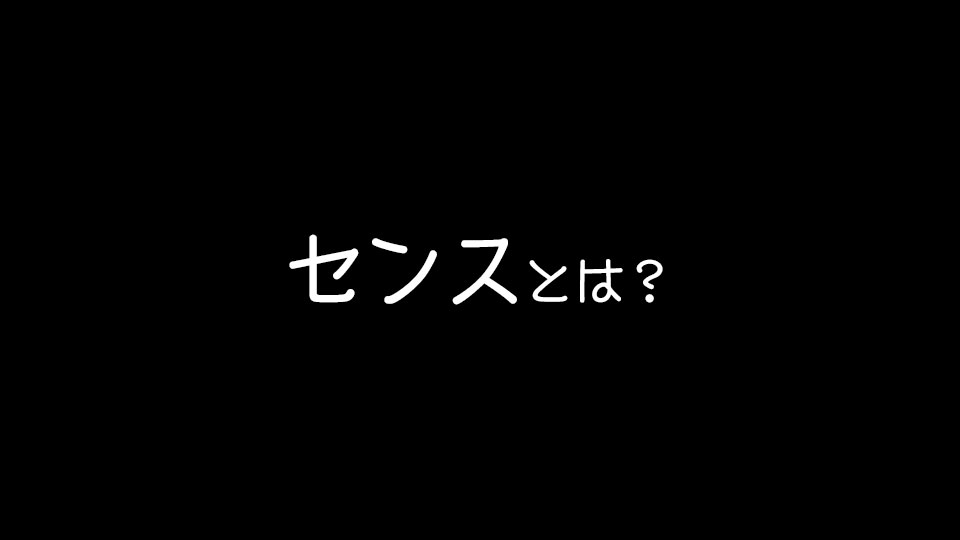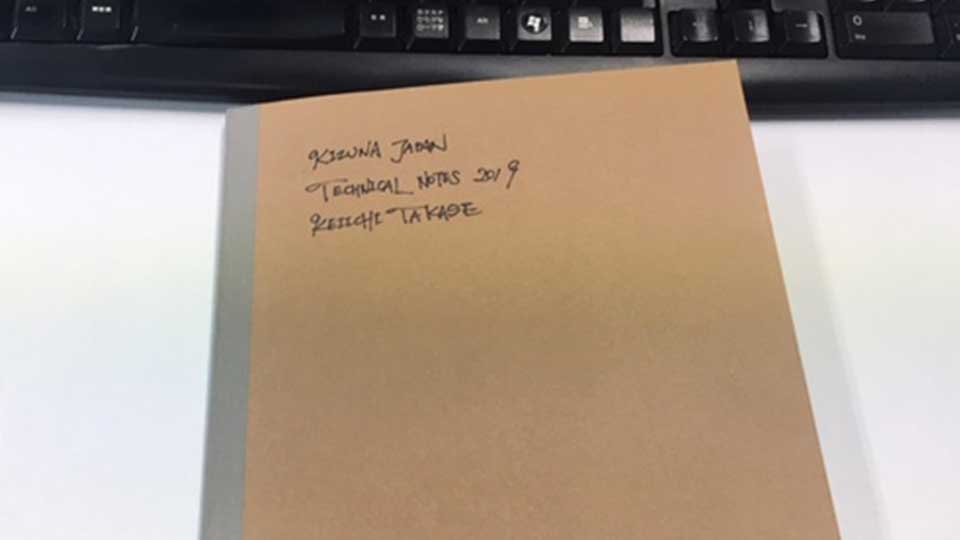近年跳ねた映像技術の一つに、立体映像というのがあります。
いわゆる、3Dですね。
近年で最も話題になった印象があるのは、
2009年の『アバター』でしょうかね。
今回は、その歴史について、ご紹介したいと思います。
撮影技術については、1830年代には立体画(ステレオグラム)の論文が発表されていて、その後10年程度で商品化されています。
日本で言うと、天保年間。
江戸時代には、その技術が既にあったということなんですね。
映像に活用され始めたのは、20世紀に入ってからになります。
1922年には、『The Power of Love』という映画が制作されていますが、
この時代、音声がまだついていません。
今考えると、2Dを3Dにする方が難しいイメージがあるんですが、
音声をくっつける方が、技術的には難しかったんですね。
その後、劇映画として本格的に制作されたのが、
サスペンス映画の神様としても名高い、『サイコ』などの映画で知られる、
アルフレッド・ヒッチコックが監督をした『ダイヤルMを廻せ!』です。
日本においても、1953年に2作品が3D映画として発表されています。
それが、『私は狙われている』と『飛び出した日曜日』です。
それ以降も、3D映画というのは、ちょくちょく発表されているのですが、
特に大きな話題になることもなく、という状態でした。
その後、革命的に大ヒットしたのが、
2009年のジェームズ・キャメロン監督の『アバター』でした。
この映画が、なんと歴代興行収入1位の2385億円の大記録を達成したので、
各方面で3D映画が流行ることになります。
そんな感じで、歴史を紐解くと流行のきっかけやら見えてきて面白いですよね。
以上!皆さんご存知、あの安部でございました。